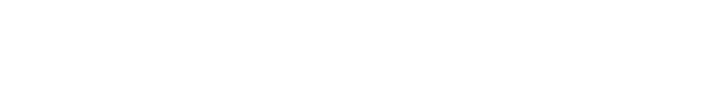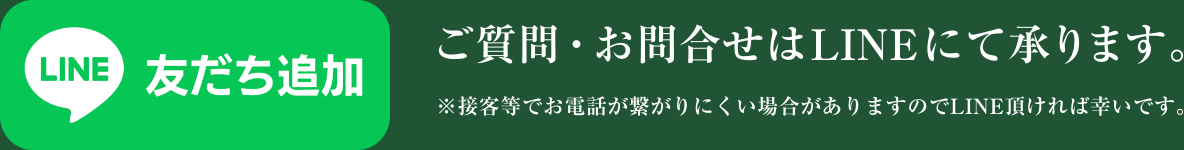限界集落から消滅集落になるのを待つのではない。商いで、未来を描き、次世代にも繋げるむらづくりを。
誰かが畑山を表現するとき、決まって「限界集落」という言葉が出て来る。
人口の数字で見れば
定義上、そう位置づけられるから。
しかし、私たち住民はその言葉に悲壮感を感じることはない。
だって、畑山の未来は輝いている。

靖一さんの目に映っているのは
幼い頃からの記憶が重なり合う風景だ。
それは想像ではなく、実際に歩んできた道のり。
色彩だけでなく、木々を渡る風の音や、
土の香り、季節の移ろいまでもが
今の風景に鮮やかに織り込まれている。
私だって、故郷での記憶はそうだもの。
でも、私にとっての畑山の過去は
まるでセピア色の古い写真のよう。
その上に、靖一さんたちの思い出話を
少しずつ色づけていくような感覚だ。
しかし、今の畑山の景色の中に、
私は確かな未来図を見ている。
他の人の目には見えないかもしれないが、
私の心には、賑わいに満ちた
鮮やかな畑山の姿が描かれている。
こんな寂れた集落で
何言ってんの?
って思う人もいるだろう。
今を見れば、仕方ない。
長く、中山間地域の振興策が語られてきたけれど
イベント倒れになってきたことも多い。
一つには、
稼ぎ出すモノを見つけられないから。
外からただただ支えられるお金ではなく
田舎の良さをきちんと伝えて正当な対価としての
お金を得られる仕組みがないから。
畑山には
靖一さんたち
はたやま夢楽が築きあげた
土佐ジローがある。
東北の震災後、倒産しかかったこともあるけれど
なんとか持ち直すことができつつある。
それは、土佐ジローに真価があったからだと思う。
余裕なんてなかった。
驚くようなジローのエサ代の請求書。
お金をかき集めて
どう支払っていくかを悩んだ毎日。
限界集落での商いは
私なんかの力量では
難しい局面がたくさんある。
ジローならまだまだやれると思えるのに、
危なっかしさは、いつも付きまとう。
ジローでは
できそうで、できない。
そんなことの繰り返し。
でも、ジロー以外に畑山再生のカードを持ち合わせてはいない。
麻薬のようなものかも知れない。
ジローがなければ、とっくに畑山から出て行っていただろうし
私が畑山を知ることもなければ、嫁に来ることもなかっただろう。
限界からの起死回生。
それができたら、スゴイじゃないかと思う。
ジローならできると思う。
不可能な未来なんて無い。
自分が描く未来を、いかに実現させていくか。。。
経営者として名をはせた人たちの
言葉には、よく出てくるものだ。
為せば成る
為さねば成らぬ
何事も
成らぬは
人の為さぬなりけり
心想事成
稲盛和夫さんの講演録にも
強い思いを持つこと、
ストイックに求めること
が収められている。
はたやまの明るい未来。
描き続けたいと思う。